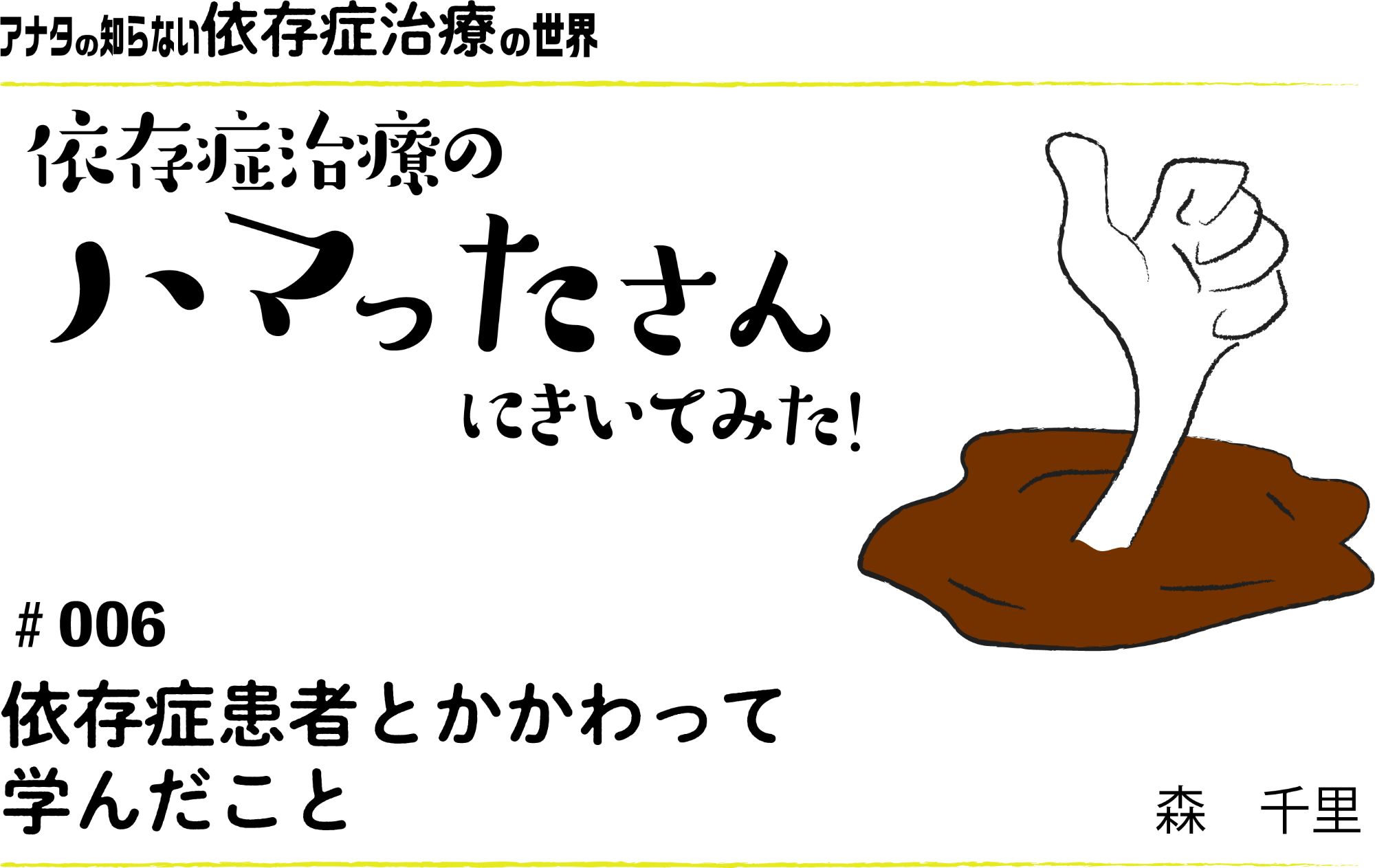依存症の患者さんって?
早速ですが、依存症と聞いて、みなさんはどのようなイメージを抱くでしょうか。
精神科に勤務している私でも、依存症と聞くと、「自分には関係のない、違う世界の人たち」「意志が弱い性格の問題」「自分でなったのだから自業自得」などのよくないイメージが強くありました。病棟医長が依存症担当医にもかかわらず、私は依存症の患者さんに無関心で、自分の勤務時間帯で面倒に巻き込まれなければいいなと思う程度でした。
しかし、そんな私も無関心でいられなくなるときがやってきました。依存症の患者さんを担当看護師として受け持つことになったのです。
私が初めて担当した患者さんは、本当に困った方でしたが、依存症を考えるきっかけを与えてくれた患者さんでもあります。その人に出会わなければ、今でも依存症の患者さんへの無関心や偏見、苦手意識を抱えたままだったと思います。この場では初めて依存症の患者さんと向き合うことになった私の心境や、そのときには気づけずにいた患者さんの気持ちを、振り返ってみようと思います。
その患者さんは30代の女性(Aさんとします)で、アルコール依存症の患者さんでした。
両親はアルコール依存症で他界しており、兄妹とも音信不通のようでした。Aさんは有名大学に通っていましたが、卒業はせずに就職。以前の交際相手から暴力を受け、水商売の仕事を強要されていたことが心理的外傷となり、習慣的に飲酒していました。
映画などで過去の似たようなシーンを見たときや、交際相手との口論で、フラッシュバックがたびたびあったそうです。急性肝炎の治療後にも再飲酒や過食嘔吐が止まらず、当院での治療を希望して入院されました。
さあ、どうしよう。アルコール依存症ってどうかかわるの? 何をしたらいいのだろう。私は依存症の患者さんとかかわるスキルをなにひとつ持っていません。カルテから入院前情報を読み取った後、依存症の患者さんへのマニュアルを探したくて、私の心は不安でいっぱいでした。私は患者さんを前にして、「私にはこの人の気持ちがわかるはずはない」と感じ、入院後しばらくは差し障りのない会話を重ねて様子を見ているだけでした。
入院後Aさんは静かに過ごしていましたが、私や病棟の看護師を何度も困らせる行動を繰り返したのでした。
入院後も飲酒を続ける患者さん
当院では依存症の患者さんが参加するプログラムがあり、Aさんも参加していました。開始後すぐに「昔の嫌なことを思い出して」と泣き出し、病棟へ戻ってきました。その後、散歩へ出ましたが、帰院時には足元はふらふらで顔面は紅潮しアルコールの臭いをさせていました。散歩中に飲酒し、病棟へも缶酎ハイ1本を持ち込んでいました。
Aさんは「プログラムが嫌。無駄だし病院にいても意味がないから退院する」と訴えました。私も含め病棟の看護師は、「これだから依存症は困る。約束を守れないし、だらしない」「何のために入院しているの。そんなに飲みたければ退院すればいい。」という感情でした。当然、主治医からも退院が言い渡されると思っていました。
しかし、主治医がAさんへ向けて発した第一声は、「よく戻って来たね!」という言葉でした。私は正直なところ「何言っているの? ルールを破ったから退院でしょ?」と、困惑と同時に怒りを感じました。
その後もAさんは病棟内で喫煙したり、幾度となく病棟にお酒を持ち込もうとしたり、外出中の再飲酒を繰り返しました。自分の水筒にお酒をジュースなどと混ぜて持ち込み、病棟内での飲酒もありました。泥酔時には、状態観察のため一時的に保護室へ隔離となりましたが、基本的には長期間の外出制限はかけず、飲酒時には自己申告という方針でした。
しかし、飲酒後の自己申告はないことが多く、私はAさんの入院継続に意味を見出せずにいました。そして何度も病棟のルールを破るAさんに対して嫌悪感が増していきました。そもそもお酒をやめたくて入院しているのに飲むのが悪い。ならば断酒を目標に介入しよう。ついに私はAさんとかかわる決心をしました。
断酒すれば解決するのに
まずはAさんを知るために面談を重ねました。音信不通の兄妹のことを考えて不安定になり再飲酒したこと。お酒に逃げたくなる気持ちを紛らわそうと外出中はウォーキングに励んでいたと知りました。面談を続け、少しずつ関係性が築けていると感じていましたが、Aさんの反応が怖くて断酒は切り出せずにいました。
そんなある日、「今の自分は違う。前のような本当の自分を取り戻したい」と泣くAさんを見て、私のなかで断酒説得モードにスイッチが入りました。「お酒やめましょう。Aさんの人生にお酒は邪魔でしょう?」と繰り返し伝えました。
しかしAさんからは、「少しだけならいいと思う。友だちとだったら楽しく飲める」との返答でした。私は「変わる気あるの?」と腹立たしい気持ちになりました。主治医にAさんが断酒すると言ってくれないと相談してみましたが、「それって片思いの相手が自分のことを好きって言ってくれないのがムカつくのと同じだから」と言われました。私は納得したような返事はしたものの、いら立ちは消えずにいました。
再飲酒の申告には表面上、称賛していましたが、とうとう入院中に1回もAさんからの断酒宣言を聞くことはなく、心の中にモヤモヤがたまったままでした。Aさんはアパートで自立した生活をする方向で退院へ向けて進み出しました。外泊中の飲酒はありましたが、単身生活とバイトの両立ができるようになり退院を迎えました。
Aさんの退院は嬉しかったのですが、断酒を達成していないことがずっと心に引っかかっていました。その後も依存症患者さんにかかわるたびに、「どうしてやめないの?」と患者さんを責める気持ちを抱き、苦しい日々が続きました。
依存=悪ではない?
Aさんの退院からしばらくして、私は自助グループに初めて参加しました。そこで依存症当事者のお話を聞きました。「酒はやめているけど毎日が苦しい。今日1日を飲まずに過ごせた。でもそれを積み重ねなければならなくて気が狂いそうになる」と聞いて、「え! 噓でしょ。お酒をやめたら人生がバラ色なんじゃないの?」と衝撃を受けました。なぜならずっと依存対象は悪だと思い、手放すよう患者さんへ勧めてきたからです。
「違うみたい。どうしてなの。もしかして私、間違っていたの?」と混乱しました。さらにほかの当事者から、依存対象は心の「よりどころ」みたいなものだと聞きました。私は「そんなに大事なものだったの? それを奪おうとしていた。私だって自分の『よりどころ』を手放せと言われても無理だし嫌だ。手放す代わりにほかのものがほしいし、よっぽど決心してもできない」と思いました。
私はAさんに自分勝手な理想や期待を押し付け、自分が正しいと思う方向へ誘導して、「断酒します」との言葉を引き出したかっただけでした。断酒はAさんの望む目標ではなく、私が設定したものでした。
私は自分の力でAさんを変えようとして、思いどおりにならないといら立ち、失望していました。自分の理想とする完璧なAさんを望んでいたからです。でもそれはありのままの患者さんではないと気づき、そこからずっと心にあったモヤモヤが晴れていくのを感じました。また、再飲酒に関しても指導しなければとこだわりすぎていました。
主治医はよく、「自分だって失敗するし、お互いに許せたほうが楽でしょ」と言っていました。当初は「何をのん気なことを言っているの」と共感できませんでしたが、自分だってダイエットのひとつも達成できないような人間なのです。間違いもするし、失敗もします。
それなのになぜ患者さんの失敗は許せないのか。それはおかしいと素直に受け入れることができました。Aさんが再飲酒したときも、繰り返さないための対策や反省を求めてばかりで、飲酒してしまったAさんの思いに寄り添うことができていなかったと、改めて思いました。
また、Aさんは入院中の気持ちの変化をたくさん私に話してくれました。その変化は今まで自分に時間を使うことができなかったAさんが、他者の助けを借りずに自分の力で導き出したものであったにもかかわらず、断酒という私の勝手な目標のほうを重視していました。今ならばその変化をひとつひとつ喜び、共有できたのにと思うと残念に感じます。
また再飲酒したときに、主治医がAさんにかけた「よく戻ってきたね」という言葉も、こんなに苦しみながらよく帰ってきたねという意味であることや、再飲酒を申告するのはたいへん勇気が必要で、素直に言えただけで大きな前進であること、患者さんが病院という治療の場をみずから選択し、この場にいると認めることが大切だと、後に実感しました。
患者さんとともに歩む
私はAさんと出会って、自分の価値観を患者さんに当てはめて変えようとするのではなく、まずはありのままの患者さんを認めるむずかしさを学びました。そのうえで患者さんが変わろうとするときも、今はそのときではないと動かずにいるときも、傍らで寄り添う大切さを知りました。また、失敗をしても、それは回復への過程であるとAさんは教えてくれました。私にとっては辛い道のりでしたが、依存症を知る入り口には立つことができました。
依存症は苦しい病です。患者さんたちは本当に長い間、自分とも病とも向き合っていかねばなりません。だからこそ、正しい理解と継続した支援が必要です。孤独にさいなまれて自分を支えられそうにないとき、いつも傍らに医療者がいると感じてもらえれば、それは患者さんにとって心の灯のようなものになると思います。
依存症というイメージだけでとらえるのではなく、患者さんに興味を持ち、話を聞いてもらいたい。そしていっしょに歩いていけるようかかわってもらいたいと思います。
その後のおはなし~つながりって?
依存症患者さんとのかかわりのなかで得たものは多くありますが、急に悟りを開いたかのように自分が変われるわけではありません。しかし以前のように患者さんを指導しなくてはと変な使命感に駆られることはなく、患者さんといっしょに悩み、困り、落ち込み、喜びを感じることができます。
以前の私は、周囲に対して正しくあろうと取り繕っていた気がします。今では自分の素直な思いを少しずつ患者さんへ伝えられるようになりました。素直に、正直に人と話すことは、案外むずかしいです。依存症の患者さんもそれが苦手な人が多いので、いっしょに練習をしている感じです。
病棟にいると、退院後の患者さんの姿はあまり想像できません。主治医は、患者さんたちに「死ななければいい。つながってくれていればいいから」と言います。「でも生きていても体が壊れたら……」と思い、私はまた理解できずにいました。
Aさんは退院後、途中から外来へ来なくなり1年ほど経過していました。先日、主治医が連絡を取る機会があり、私も同席させてもらえました。Aさんは元気そうな声で、「入院中は本当に迷惑をかけてごめんなさい。あのときの自分はどうかしていました。今は働いてちゃんと暮らしています。先生と看護師さんの顔が浮かんだから、外来行こうかな」と言っていました。それを聞いて、「本当に生きていてくれてよかった。私はAさんに感謝していることがたくさんあるよ」と心の底から思いました。
入院中、Aさんに振り回され困った日々も、話を聞きすぎて疲れたことも、こうして時間が経っても再びつながるために必要だったのだと感じました。久しぶりの連絡がAさんの心に小さな灯となった気がするとともに、私の心にもAさんが灯をともしてくれました。
依存症のいちばんの敵は孤独です。一人ではどうしようもなくなり、みずから命を絶つ人も多い病です。しかしどんな状態でも、人とさえつながっていれば、回復の道を再び歩むことが可能な不思議な病でもあります。依存症に立ち向かうには、患者さんも、家族も、支援者もつながり続けることが必要です。回復に際してこれだけ人の力が重要な病もないなと思いながらも、私もそのつながりのひとつとなれるよう、患者さんと向き合っていこうと思います。
昭和大学附属烏山病院 看護師。