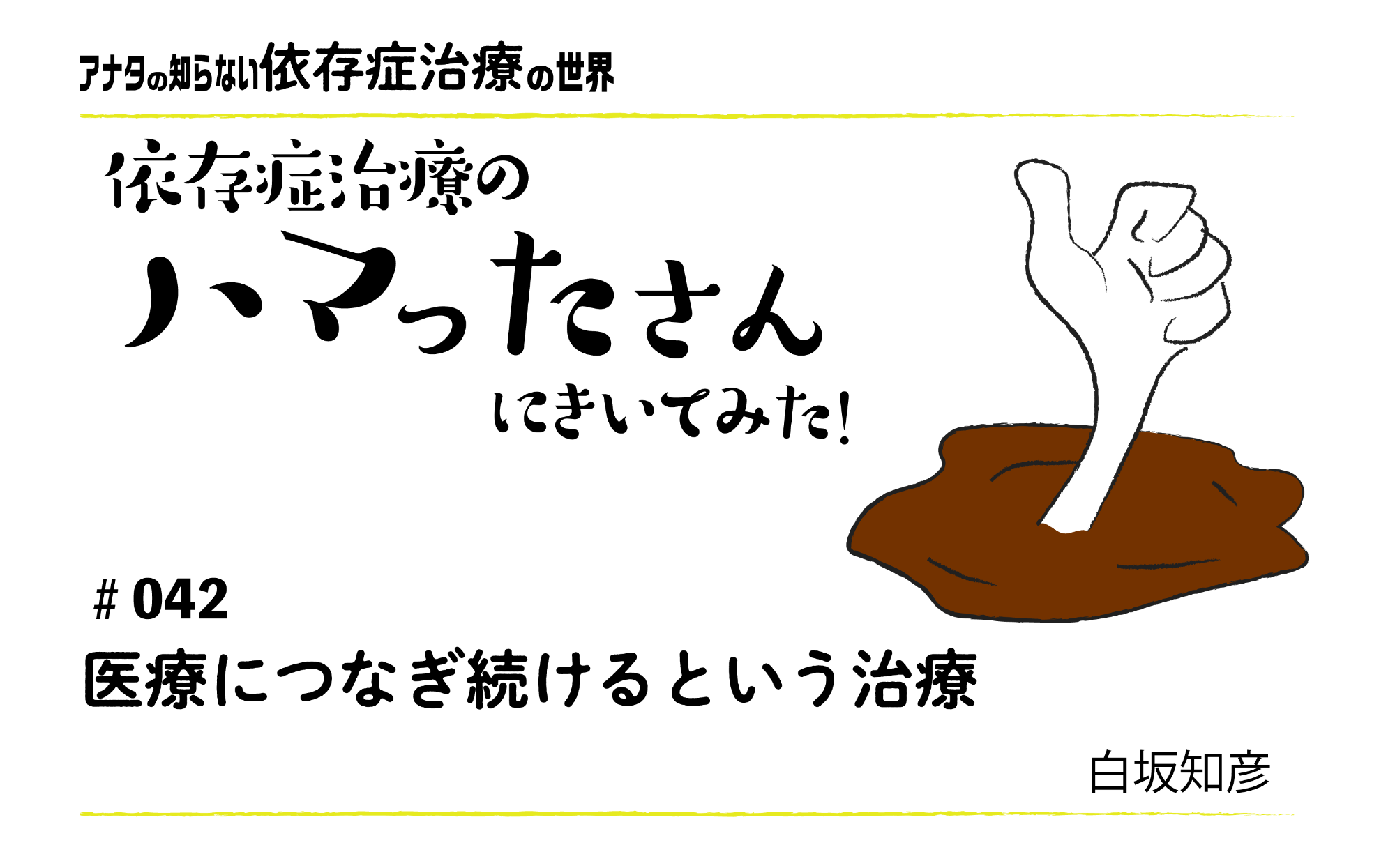1.飲酒をやめないAさんへの治療で感じた戸惑いと不毛さ
私は精神科医師として大学の医局に所属し、数年単位で異動をくり返してきました。転勤先はいずれも地域の中核総合病院でした。臨床研修も含め20年ほどの医師生活のなかで、今でも忘れられない患者さんがいます。
それは、まだ私が精神科の専攻医だったころのことでした。当時勤めていた依存症専門病院では、しばしばアルコール依存症患者さんの外来診療を担当していました。とはいえ、私はまだ依存症についてほとんど何もわからない20代そこそこの若造で、患者さんたちは皆、アルコール依存症という疾患においても、人生経験においても、歴戦を重ねてきた「猛者」ばかり。その「猛者」の一人にAさんという患者さんがいました。なお、プライバシー保護のため、Aさんの詳細に関しては多少のフィクションを交えて書いています。
Aさんは毎回、明らかに酔っ払っているのに「先生!お酒飲んでいません!ゼッコウチョーです!」と言いながら診察室にやって来ました。通院はしているものの飲酒をやめない、院内でも有名なアルコール依存症患者さんでした。依存症についての知識も経験も少なかった私は「この人に、このまま治療を続けて意味があるんだろうか」という疑問をもっていました。
多くの病院がAさんのような患者さんに対しては「お酒をやめる気がない人が通院しても意味がないから、お酒をやめてから改めて受診してください」と言って追い返し、底付きを待つという方法を取っている時代でした。そっちのほうが正しいのではないか、そう考える私に外来の師長は「医療につながって、病院に来るだけですばらしいことなのよ」と諭してくれましたが、そのころの私にはその言葉の意味がまったくわかりませんでした。
師長が言うならそうなんだろうと自分を納得させつつも、正直なところ、Aさんへの治療は今後に何の進歩も望めない不毛なかかわりという気持ちが消えませんでした。
2.自分を見下すAさんに平常心で接するうちに、Aさんにある変化が…
ある日、仕事帰りに夕食を食べようと近くのレストランに立ち寄りました。パスタを注文して待っていると、なんとAさんがホステスさんらしき綺麗な女性といっしょに店に入ってきたのです。そして、私の存在にはまったく気づかず、女性とワインで乾杯しながら「今度来た新しい精神科の先生は若くて全然怖くないし、適当にあしらっておけば良いから楽でいいわ」と大声で話していました。それを聞き、なぜか私のほうが見つからないように急いで食事を済まし、こそこそと帰りました。私に対するAさんの評価が本当に頭にきて、マイナスの感情でいっぱいになったことを覚えています。
しかし、その後の診察ではあの夜の出来事には触れず、ただ、週に1回顔を突き合わせ、「先生!お酒飲んでいません!ゼッコウチョーです!」というおなじみのセリフとAさんの世間話を聞き続けました。
そのなかで、Aさんが、家族の話をしたときがありました。Aさんは自分に双子の弟がいることをずっと知らずに生きてきたそうです。知ったきっかけは病院からの電話でした。双子の弟は生活苦のために養子に出され、裕福な家庭に引き取られましたが、アルコール依存症になって家族との関係が断絶。弟の入院していた病院が血縁者を探してAさんに連絡してきたのです。Aさんは病室で自分と同じ顔をした兄弟と初めて出会い、一人で弟の最期を看取り、荼毘に付したと話しました。「まったく違う環境なのに兄弟ともアルコール依存症になり、同じ顔の弟は先に亡くなって自分は生きている。もし、養子に出されたのが自分のほうだったら今ごろどうなっていただろう」とポツリと言い、その日はもうそれ以上話しませんでした。
3.Aさんが突然の断酒!いったい何が起こった?!
相変わらず、話を聞くだけの診療を続けて数カ月後、突然Aさんはシラフで病院に来るようになりました。誰の目にも明らかなほど、以前のAさんとは様子が違っています。その変貌の理由がわかったのは、私の転勤が決まってAさんの主治医を交代することになったときでした。
最後の診察で、私はどうしても気になっていたAさんの突然の変化について尋ねました。「Aさん、ずっとお酒やめなかったのに、ある日を境にまったく飲まなくなっていったよね?いったい何があったの?」。
Aさんは「先生、気づいていましたか。今までは酒がやめられなくて、もうやめる必要もないとすら思っていたんだけど、ある日、それまでと同じように酔っ払って倒れて救急搬送されてね。病院のベッドに寝ながら点滴の雫が一滴ずつ落ちるのを見ているうちに、今まで酒のせいで人に迷惑をかけた自分の人生が走馬灯のように流れてきたんだよ。それで、もう酒はやめようと思えたんだ」と静かに答えました。
4.患者さんの生き直す力を信じて、医療につなぎ続けることが大切
Aさんの話に私は衝撃を受けました。なぜなら、アルコール依存症の患者さんは飲酒をとことん後悔するような「底付き体験」をしないと酒をやめることができない、と教わっていたからです。アルコール依存症の治療とはそういうものだと思っていながら、師長に言われるままに「通院することを評価し、否定せずに話を聞くだけ」の診療を続けていたために、若く未熟な私は悩みもしたのですが、実際に、Aさんは「底付き体験」なしで変わったのです。
そして、この印象的な出来事は、私がAさんとかかわる前から、多くの主治医がAさんの飲酒を咎めずに全人格を受け入れ、回復を信じて寄り添ってきた積み重ねがあってこそ訪れた転機なのだと気がつきました。
私はAさんの診療を通し、アルコール依存症治療において患者さんを医療につなぎ続けることがどれほど大切かを学びました。そして、Aさんが新しく人生を生き直そうとする瞬間に立ち会えた経験から、「人はいつからでも変わることができる」ことを信じるようになり、アルコール依存症治療にハマって今に至ります。20数年前のあの日々を振り返るたびに、Aさんに「先生だって変われるよ」と背中を押してもらっている気がします。これからも変化を恐れず、与えられた環境の中で自分なりにできることを、患者さんや患者の家族といっしょにやっていきたいと思います。