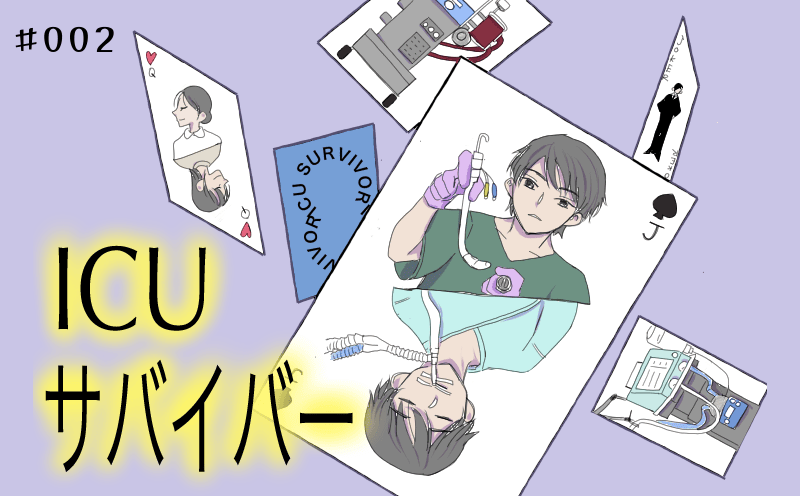主人公は、麻酔科医としてICUで勤務していた。しかし、ある件をきっかけに自分が「擬似患者体験プログラム」の参加者として、ICUに入室した患者側になることに……。
擬似患者といいながら、気管挿管にリハビリや清潔ケアなどリアルなICUを患者として体験する主人公と家族、医療者に様々な想いが交差する。
同じ物語を小説版と漫画版の双方で楽しみながらICUを学べるコンテンツとして発信中!
小説は本ページで、漫画はinstagramで公開中。
第二章:日常はいつだって、誰かの非日常
ICUは、どこか静かで、そして同時にざわついている。
申し送りの声、電子カルテを打つリズム、看護師が患者の背中をさする布のこすれる音。
人工呼吸器のアラームが鳴ったかと思えば、別のベッドではレッドアラームが鳴り響く。けれどその正体は、一生懸命に歯を磨く患者のノイズだったりする。
日常と非日常が同居している。それが、僕のいたICUだ。
音はそれぞれが勝手に鳴っているのに、不思議と同じ方向に流れていくような気がする。その奇妙な一体感は、ICUにいるときだけ感じられる特別な感覚だった。
スクラブの袖を引き上げながら、僕はその流れの一部に溶け込んでいた。
ICUには、準備運動や助走なんてものはない。始業のチャイムもなければ、ちょっとコーヒー飲んでから……が許される余白もない。気づけばもう、次の一手が始まっている。
「あ、高遠先生! 見てください、座れました!」
昨日、遅くまで起きていたせいでまだ眠い僕に、声が響いた。

視線を向けると、人工呼吸器を使っている患者がリハビリでベッドサイドに座っている。
理学療法士が体を支え、看護師がチューブを抜けないように手で添え、声をあわせ「せーの」と掛け声をかけていた。
かつて救命も難しいと考えられていた患者だ。もうベッドサイドに座ってもバイタルは崩れない。しかしながら重い腰は、ほとんど理学療法士が持ち上げているようなものだけれど、それでも立てた事実に看護師が嬉しそうに声をかける。その声に応えるように、理学療法士も穏やかにうなずいていた。
隣のベッドでは、作業療法士が大きなテーブルを用意し、ベッドを起こしながらスマホの画面を操作していた。
高齢の患者は、片麻痺で姿勢の保持や指の運動が困難な様子だが、そもそもスマホの扱いに慣れていないのだろう。それでも孫に治療を頑張っていると伝え、孫の写真や動画も見たいのだという。
作業療法士の姿勢は前のめりで、まるで家族の気持ちを一緒に運んでいるようだ。
さらに奥では、ECMOの回路交換を前に、臨床工学技士が黙々と回路の確認を繰り返していた。
今日は予定された回路交換だから、比較的穏やかに準備がされている。ちなみに、緊急時におけるECMOをプライミングする臨床工学技士の動きといったら、まさに武田信玄の「疾きこと風の如く」を思わせるほどだ。
横では、新人看護師が医師の着るガウンの紐をもたつかせている。
先輩看護師が「そこ持って、動かない! 先生が動くから!」と、鋭くも頼もしい声を飛ばしていた。
反対側では、酸素化が悪化した患者の気管挿管が決まり、家族を待っている。
患者は肩を上下させて呼吸をしているが、意識は明瞭で、看護師に何かを伝えようとしていた。
「家族が来たらお話しましょう、少し深呼吸しましょうか」
と、モニターと患者を往復する視線と共に、看護師は意図として努めて落ち着いている声を出しているようにもみえる。
主治医は電話で家族を呼んでいるようだ。丁寧に声をかけ来院を告げている。
少し離れたところでは、麻酔科医であり集中治療医でもある僕の先輩医師が、気管挿管を控えカルテを確認しながら静かに待機していた。
また別のベッドでは、薬剤師と医師が血中濃度について短く言葉を交わし、栄養士が資料を手に通り過ぎていく。
足を止めたのは、患者のベッドサイド。
昨日NSTカンファレンスで検討してつけた補助食品だったが、甘すぎて食べられないということだ。ICUの患者にとって栄養は重要だ。食欲のない患者が少量でも栄養を摂れるように工夫した補助食品、その甘さが仇になってしまったのだ。
出入口に近いベッドでは、手術翌日の患者が病棟へ退室する準備が進められている。
看護師が点滴ラインを整え、主治医が「無事、手術終わりましたから病棟へ戻りましょう」と声をかけると、患者はわずかにうなずいたように見えた。
ICUには、それぞれの物語がある。それらすべてが、僕にとっては日常だった。

誰かの状態が乱れれば、時間はそこだけ早送りされる。
逆に、何も起きていないように見える瞬間もある。でもそれは、僕たちが慣れてしまっていただけなのか、はたまた何も起こさないようにスタッフが尽力している結果なのかもしれない。
―――
「おはようございます、高遠先生」
背中にかかった声に振り返ると、看護師の梓川七海がワゴンを押していた。
ワゴンの上には、使い終わった清拭用のタオルが置かれている。ついさっき、誰かの清拭を終えたばかりなのだろう。
「あ、おはようございます。えと、あっちで挿管、するんですかね」
僕は、遠くにみえる先輩麻酔科医の唐沢彩先生を見ながら言葉をつないだ。
「そうみたいですね。挿管しなきゃな酸素化で。ご本人も希望されたようですけど、まだ少しなら余裕があるから、ご家族とお話してからって言ってました。高遠先生が挿管するんです?」
梓川は足をとめ、柔らかく問いかける。彼女の声は穏やかで、相手を急かす色をみせない。落ち着いた調子のまま、必要なことを引き出すことが多い。
「そうしようかなって。唐沢先生、当直明けですしね」
「たしかに! でも唐沢先生なら高遠先生に任せても、きっと見守ってくれそうですね」
ふと、目が合った。笑顔の奥に、仕事の緊張を支える芯のようなものが透けて見える。
その瞬間、胸のどこかが不意にざわついた。
「はい、僕も行って頑張らないと」
そう言いながらも、足は動かない。
唐沢先生が気管挿管に使うマックグラスを取り出す姿が見える。挿管の準備は、ほぼほぼ整っている。それでも、まだ家族を待っているのだから。ほんの少し、ここに立ち止まっていてもいいだろう。
そう思ってしまう自分は、きっと甘えている。
「……梓川さん、今日はリーダー?」
「今日はRRSの当番です。呼ばれる前に、できることやろうと思って」
RRS、Rapid response system──病院内で急変した患者に対応したり、急変予兆として迅速に療養場所の選定や対応を行うチームのコール番。
それを担う彼女は、現場でもよく頼られる存在だ。
「RRSの医師は……今日は入野先生でしたっけ」
「そうです。昨日RRSでICUに入った患者さん、今朝から痰が増えてるみたいで。脈も速いし……このあと様子見て、入野先生に相談しようかなって」
少しだけ声のトーンが変わる。観察と判断の狭間で、彼女の頭の中にはすでに次のアクションが組み立てられているようだ。
「入野先生、呼吸器内科出身の集中治療医だから。こういうところで活躍してもらわなくっちゃ、ですよね」
その横顔に、まだ言葉を投げたくなる。けれど、ここから先はもう彼女の時間だ。
笑顔を残しながらワゴンがゆるやかに動く様子を見て、会話を切り上げる。
「そうですね! じゃ、僕も唐沢先生のところに行ってきます」
後ろ髪をひかれる思いを抱えながら、足取りは少し早めに。名残惜しさを隠すには、それしかなかった。
―――
梓川は、高遠が小走りに上級医の元へ向かう背中を見送りながらワゴンを片付け、昨日自分が対応した患者のベッドサイドに足を運んだ。
呼吸は人工呼吸器のリズムに乗り切れていない。心電図の波形は一見整っているのに、速すぎる鼓動が胸に不自然な影を落としていた。胸郭の動きも、どこか浅い。
ちょっと、呼吸、浅いかも……
そう思いながら視線を胸郭と同じ位置まで下げると、前日よりも悪くなっているように見える。
ゆっくりと視線を戻しながら考える。
酸素化は保たれている。でも、色々な体のリズムが少しずつ狂っていくような気配が漂っていた。血液ガスのデータがパソコンに一覧として並んでいる。
先ほどとられた動脈血ガスの値と、少し前に取られた中心静脈血の値だった。
SaO2は保たれている。でもSvO2は、明らかに下がっている。
循環器内科の指示で取られた値が、逆に今の変化を鋭く映し出していた。
四肢の末梢は冷感があるだろうか、じっとりとした汗などはかいていないだろうか。
ベッドの近くには、今日の担当看護師である望月がいた。
先ほどの高遠医師と入職同期だが、年齢は望月の方が下であり、看護師としては数年目。
それにしても最近の男性看護師はみんな似た髪型をしているものだ……と、パソコンを見つめる彼の髪型を見ながら思った。望月の眉間には深いしわ。でも答えにはまだ届かず、その迷いだけが顔に残っている。
望月は日頃からやる気があり、先日学会が推奨するICRN(集中治療認証看護師)という重症患者に対する看護実践や、看護に必要な知識があるという証ともいえる試験に合格し、喜びの報告をくれた。
そんな望月が何かを考えている。
でも、その考えが不明瞭なのか眉間のしわは深くなるばかりだ。声をかけてみるか……。
「望月くん、どうしたの?」
穏やかに、でもやや語尾を上げて声をかける。
「お、梓川さん! 今、いいっすか?」
「うん、いつでもいいよ」
彼の返事には、迷いと助けを求める色が混ざっていた。
「なんか変なんですよ。肺音聞いたんですけど、痰はないし。でもなんか苦しそうだし。尿も少ないけど、出ちゃいますし」
望月は患者を見ながら、言葉を選ぶように話し始めた。開かれているパソコンの画面にはデータが並んでいる。
「今は、採血のデータ見てたんだ。血ガスに、中心静脈血ね。前回の値とか、その前と比べたらどんな感じなのか教えてくれる?」
画面を一緒にみながら、梓川はまだ患者のデータを知らないといった口ぶりで望月に尋ねた。
「はい、酸素化はそんな変わらないっすね。んー……あ、前と比べるとvO2下がってますね」
「あぁ……ほんとだね。患者さんの状態は……触ってみた? 昨日に比べたらどうなの?」
「体は……皮膚は冷たいのに、汗かいてるんですよ。あとは、昨日に比べたら、脈のベースも……上がってますね。あと、平均血圧も、なんとなく下がり気味……ですね。あ、尿も出てるけど減ってきて……」
経過表を数時間前や昨日に戻り動かしながら、望月の瞳は大きくなっていった。
言い終わったあと、彼は一度息をついた。
梓川は、その横顔を見守っていた。答えを出す必要はない。ただ、その気づきが今まさに、形になろうとしていることが大切だった。
「……心不全の、増悪、ですかね。夜は一旦良くなってたけど、また悪くなってきてますかね」
その言葉をようやく自分の口から出したとき、望月の声は早く対応しなければならないという気持ちと考えが閃いた喜びも感じた。そこには確かな根拠と過程があった。
「うん。私も、そう思う」
梓川は、笑わずに答えた。誤魔化さずに、まっすぐに。
「確かに尿はでているけど、体はdry・wetだよね。SvO₂の低下、脈拍、平均血圧……全部、根拠になるよ。たぶんこのままじゃ、このあと呼吸も循環ももっと崩れる」
彼女の声は静かだった。でも、その静けさが、望月の思考に確かな輪郭を与えた。
「先生に相談、してきます!」
「そうだね、さっすがICRN」
「え、ちょ、やめてくださいよ〜」
望月は照れながら小走りに医師のもとへ向かった。
「めっちゃ頼りにしてますよー。行っておいでー」
望月を見送ると同じタイミングで、RRSのコールが鳴る。
「あ……、はいRRSの看護師梓川です。……はい、えぇ。……はい、血圧低下。すぐお伺いしますね」
重症じゃないと良いと思いながらコールをとり、近くにいた入野を手招きする。
入野は大きな恰幅のよい体を揺らしながら近づいてきた。
「……入野先生、西病棟で発熱・血圧低下です。昨日、尿路感染で入院した方だそうです。敗血症ですかね? ひとまず、行きましょう」
「へい〜。俺これからNSTの回診やったのに」
「大丈夫、リーダーが私のRRSコール鳴ったことに気づいて、栄養士さんに遅れるって、向こうでもう連絡してくれてますよ!」
後ろではRRS独特のPHS音が鳴り響いたことに気づいたリーダーが、すぐさま栄養士に連絡していた。リーダーは、大丈夫とでも言うように梓川を見ながら軽く手を挙げ微笑んでいた。
その近くでは望月が主治医と落ち着いた様子で話していた。
大丈夫と思えるスタッフがいること。それが梓川を、RRSに向かわせる一歩の背中を押していた。
「ありがとー! 西病棟行ってくるね。また入室するか状況みて連絡するね」
「はーい、いってらっしゃい!」
リーダーに声をかけ、ICUを振り返る。
高遠が唐沢と並び、挿管の準備を整えているのが見えた。
みんな頼れる仲間たち。そう感じながら、ICUをあとにした。
これが梓川の日常。
けれど、これから向かう患者にとっては―やっと慣れ始めた入院生活が再び裏返り、非日常へ引き戻される瞬間のはずだ。
―――
「唐沢先生、おはようございます。僕がやりますよ」
「お、高遠先生、おはよう! 」
僕は挿管準備をほぼ終えている唐沢先生の真横に来た。
患者さんよりも少し離れたところで、準備がなされていた。綺麗に整理整頓して並べられている。僕が追加で準備するものなどあるはずがない。
「私がちゃっと挿管して後は高遠先生にお任せしようと思ってたけど……」
「大丈夫で……」
「私がやるー!」
返事した瞬間に甲高い声とともに、安曇かなでが飛び込んでぶつかってきた。
僕より頭二つ分よりも身長が低い、小柄な同期の麻酔科医。
「おいー。安曇、今日オペ室じゃないんかい」
「午前中のオペとんじゃったんだよね。患者さん熱出たらしくて。別のオペ入ってもよかったんだけど、空いてるからICU行ってきていいよって」
彼女は目を輝かせながら、まるで遊び場を見つけた子どものように立っている。
「そうなんだ、じゃ高遠先生が挿管して、安曇先生がサポートにしようか」
「えー、唐沢先生、私の方がちゃっと挿管できますよ?」
自信満々に言い切る姿に、思わず苦笑いが漏れる。
けれど唐沢先生は改めて周囲を見回して告げた。
「残念ながら、今リハビリ真っ只中の時間で足台は全部そっちに回ってるのよ」
「あ……」
安曇の肩が一瞬しぼむ。彼女は小柄なため、ベッドの種類によっては気管挿管の時に声門が一直線に見える角度まで調整できないことがある。気管挿管でのポジション取りは、基本にして最重要。マックグラスを使えば画面越しに確認できるとはいえ、基本は大事。
それを唐沢先生から教わってきた。
安曇は自分で「せっかち」と言うが、手技は正確で速い。おまけに器用な足技まで持っていて、気管挿管の最中に足で台を蹴ってどかしたり、素早く乗ったりもする。
・・・ちなみにこのICUには、暗黙のあるあるがある。
安曇の挿管には必ず足台を用意すること。
そして、がっしり体型で大汗をかく入野先生が気管支鏡を扱うときには、室温を下げておくこと。
唐沢先生の目が笑ってないのに笑い声が聞こえる時は、本当に怒っているから迅速に対応しなければならないこと。
誰に言われるでもなく、自然とそういう空気が出来上がっていた。
「悪かったな、同期よ。そういうわけで僕の出番という訳だ」
「もうっ、譲ってやんよ!」
小さな体で大げさに肩をすくめてみせる。その仕草に、場の空気が少しだけ和らいだ。
「仲良いねー。二人が育ってくれて私は安心よ」
唐沢先生は目を細め、僕らを眺めていた。
ただの雑談に見えるやり取りの奥に、ICU特有の張り詰めた空気が流れている。
その緊張と、同期との軽口。両方が同時に存在する。
それが僕にとっての日常だった。
@icu_survivor

ICUや病棟で働く認定看護師。コロナ禍を経ていかにICUがどのような場所で、PICS(集中治療後症候群)ということも世間には全く知られていないかを痛感!物語を通して、ICUにどのような患者さんやご家族、医療者が関わっているのかを表現したいと意気込み小説側を執筆中。
instagram:(yukika_n_s)

急性期病棟を希望したら、新卒でICUに配属された猫かぶり看護師。日々仕事に励みながらICRN(集中治療認証看護師)を取得。ゆきかさんの作品に感銘を受け、今回漫画で参加。
instagram:(nekokaburikaya)