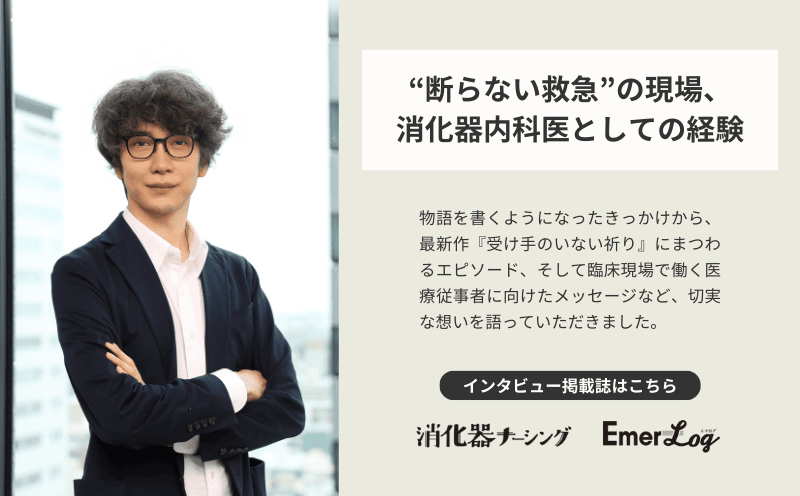医師としての経験をもとに命や病気、身体などに着眼して独創的な物語を書く作家・朝比奈秋先生。芥川賞受賞作『サンショウウオの四十九日』をはじめ、2021年のデビュー以降、名だたる文学賞を立て続けに受賞されています。今回のインタビューでは、“ 最も私小説に近い”と謳う最新作『受け手のいない祈り』の背景と、消化器内科医としての経験、創作にかける想いなどについてお話を伺いました。

朝比奈先生は、消化器内科医としての経験を経て作家としてご活躍されており、これまでの著作では人工肛門(ストーマ)、移植手術、結合双生児などをテーマに臨床医ならではの表現で独特な世界を描かれています。
今回、そんな先生の作品に関心をもった編集担当UがSNSでフォローしたことをきっかけに、先生が小社雑誌『消化器ナーシング』や読者であるナースの方々にも関心をもたれていることを知り、インタビュー実現へとつながりました。
物語を書くようになったきっかけから、最新作『受け手のいない祈り』にまつわるエピソード、そして臨床現場で働く医療従事者に向けたメッセージなど切実な想いを語っていただき、編集部一同、感激しつつお話をうかがいました。
医療従事者をはじめ多くの方に、ぜひ読んでいただきたいです。(編集部)
論文の執筆中に、とつぜん物語が降りてきた
−−消化器内科医から一転、作家になられた経緯について、お聞かせいただけますか。
30歳代半ばのころ、胃腸の論文(症例報告か何か)を書いていたときに、急にふっと物語が思い浮かんできました。Wordを開いて書き始めてみると、いくらでも思い浮かんでくるし、いくらでも書ける。その延長線上で小説を書き始めて、5年目くらいで文学賞を獲得でき、プロの作家になりました。
小説を書き始める前まではずっと理系の本や医療の参考書・論文を読んでいたので、特段“小説好き”とか“作家になりたい”という気持ちはなくて。それまでは、高校の国語の教科書で小説に触れたのが最後だったと思います。
−−これまでの著作では「命」や「身体性」をテーマに書かれていますが、そもそも医師を目指したきっかけは何だったのでしょうか。
幼いころから「人間って何やろな」とか、「死ぬってどういうことなんやろ」みたいなことをずっと考えるタイプで。もっとも古いときで、3歳くらいのころにそういった探究的な問いを抱いた記憶があります。
僕自身も病気がちで、交通事故で左の大腿骨を折って入院した時期もあったり。そんな経験も経たことで、常に命とは何なのか、病気とは何なのか……ということを考え続ける人生でした。それを自覚したときに、「こういうことを考えるってことは医者に向いてるのかな」と思い、そこから医師を志すようになりました。
医師になってからも、特に臨床現場に出ると実際に亡くなっていく人を目の当たりにするので、なおのこと命や人間について自問自答し続けるようになりました。おそらくその悶々とした気持ちが爆発して、物語が降りてくるようになったのだと思います。

−−自問自答し続けることを、どこかでストレスに感じていたのでしょうか。
周囲の誰にも話せなかったので。医学部生時代から自分がマイノリティだとは常に感じていました。小学生くらいまでは「何で人は死ぬんだ」「何で病気になるんだ」と親に聞いたりして、その場ではそれなりに答えてくれたんですけれど、納得がいかなかった。ほかの大人に聞いてもわからなかったので、もう人に聞くものじゃないんだな、と。
医学部に入ってからも、当たり前ですが周りは「医者になりたい」「治療したい」という人がほとんどでした。僕は逆で、医療的な知識や技術を学んで治療するよりも、もっと命そのものに興味があったんです。
そういう意味では少し冷めた学生でしたが、大袈裟なことを言えば、医学を勉強したところで人は治療できても「いずれ死ぬ」という事実には抗えない。なので科学的である医学よりはむしろ、自分の中にある「命とは何か」という哲学的・宗教的な興味のほうが深まるばかりでした。
インタビューの続きは本誌にて!

消化器ナーシング2026年2月号
Emer-Log(エマログ)2026年2号 →3月刊行(予約商品)
※インタビュー記事は各誌とも同じ内容を掲載しています。
今後も対談など、朝比奈先生を招いた特別企画を予定しています。お見逃しなく!
1981年京都府生まれ。医師として勤務しながら小説を執筆し、2021年、『塩の道』で林芙美子文学賞を受賞しデビュー。2023年、『植物少女』で三島由紀夫賞、『あなたの燃える左手で』で泉鏡花文学賞と野間文芸新人賞を受賞。2024年、『サンショウウオの四十九日』で芥川賞を受賞。2025年、急性期病院での過酷な労働を綴った『受け手のいない祈り』を上梓。ほかの作品に『私の盲端』など。