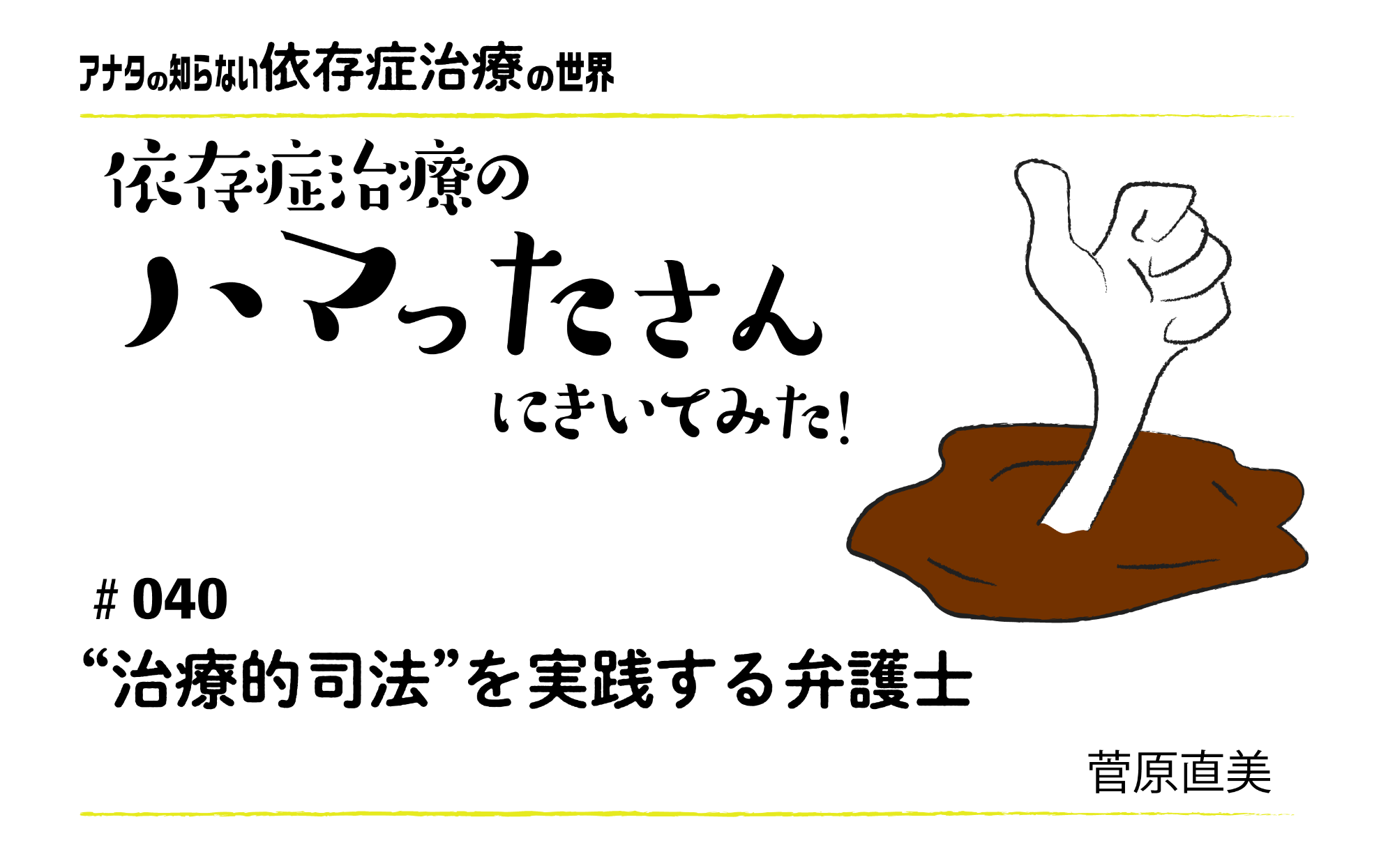1.弁護士がなぜ依存症とかかわるの?
皆さま、初めまして。私は東京都立川市で弁護士をしている菅原直美と申します。
え?!なぜ弁護士が依存症治療のコラムを?と思ったかもしれません。このコラムの読者は医療関係者が多いと聞いています。実は医療関係者はお仕事の中で、弁護士や裁判とかかわることも珍しくありません。そのときに備えて、というと大げさですが、弁護士が依存症の人たちとどのようにかかわり、医療関係者の方々にどんなふうにお世話になっているのか、私の経験から少しでも知っていただけたら嬉しいです。
2.「依存なんて『ダメ!ゼッタイ!』」の呪縛を解いてくれた笑顔
弁護士になるには、司法試験合格後に法律家になるための研修を1年間受ける必要があります。私が初めて意識して依存症の人たちとお会いしたのは、その司法修習という研修中でした。私が研修を受けた奈良県の弁護士会では、依存症回復支援施設の見学を行っていました。当時の私は、依存症やその専門施設に興味はありながらも、正直ちょっと怖いという気持ちで研修に参加しました。今思えば、依存症に対して何も知らないのに漠然とした恐怖やマイナスイメージを持ってしまっていたのは、薬物撲滅を呼びかける「ダメ!ゼッタイ!」という政策PRのネガティブな効果だったと思います。
施設にバスが到着してドアから降りた途端、その場で立ち話をしていた数人の男性が「こんにちは!」と笑顔で私にあいさつしてくれました。ここのスタッフさんかな?と思いながら施設に入り、日の光が差し込む明るい建物の中を歩いていると、すれ違う誰もが「こんにちは」とにこやかに声をかけてくれるのです。その人たちがみんなこの施設の利用者だと気づいたとき、私は見学前、依存症の人たちに対して言いようのない怖さや嫌悪感などネガティブな感情を抱いていた自分がとても恥ずかしくなりました。
その後、施設の説明を聞き、プログラムを体験しながら、私は偏見を持っていた自分を笑顔で受け入れてくれた彼らに何かお返しがしたい、弁護士として彼らの力になりたいと強く思い始めていました。これが、私が「依存症サポートにハマった」弁護士になったきっかけです。
3.医療現場が「司法」に出会うとき
弁護士になった私は、刑事事件や家事事件を通してたくさんの依存症の人たちと出会うようになります。依存症が事件の原因や引き金になることもあれば、薬物や窃盗のように依存行為そのものが「犯罪」として裁かれることもあります。これまでの刑事司法では、依存症の人たちがなぜ依存行為をするに至ったのか、どんな困難や不遇、環境要因があったのかという点は軽視もしくはほぼ無視されてきました。しかし、私は依存症の人が罪を犯したときには、その犯罪に至る背景こそが重要であり、刑事司法が目を向けるべきだと考えています。そして、同様の思いや志を持つ弁護士や研究者の方々と“治療的司法”という理念を掲げ、自分の弁護活動の中で実践するようになりました。
“治療的司法”とは、犯罪の背景事情までをよく検討したうえで、司法手続きにおいて被疑者・被告人となってしまった人たちにとってどのような治療や支援・ケアが必要かを検討し、それらを提供することで犯罪に至る根本問題を解決しようという考え方です。その結果、依存症の人たちが再犯せずに社会で安心・安全に暮らせるようになることこそ、司法が担うべき問題解決の在り方ではないかと思うのです。
この理念を実際の裁判手続きの中で実践するために、私は依存症治療や支援を行っている医師や看護師、社会福祉士や心理士など、さまざまな人たちの力を借りるようになりました。覚醒剤を使用した人の裁判で医師に意見書を書いていただいたり、窃盗を繰り返す人に対しては裁判手続きと並行して入院を依頼し、治療を始めていただいたり、今や私の弁護活動は、こうした方々の協力なしには成り立ちません。“治療的司法”的な弁護活動は若い世代の弁護士を中心に広がってきていますので、依存症を抱える人の裁判にとって、今後ますます依存症治療や支援に携わる医療関係者が重要な役割を担う場面が増えていくだろうと感じています。
4.依存症の人たちが「生き直せる」裁判システムを実現させたい
私は事件を通じて出会った依存症の人たちに、必要な治療や支援・ケアを提供したいと思いながら医療や福祉と連携していますが、日本では依存症に対する偏見や無理解、無関心によって、司法手続きの中で医療や福祉が正しく扱われない、あるいは十分に扱う時間や手段を与えられないと感じることが多くあります。
以前、“治療的司法”のつながりで出会った仲間とともに、オーストラリアでドラッグ・コートという海外の薬物事件専門の裁判を見学しました。そこでは、裁判官、医療や福祉の専門家、そして実際に依存症を抱える人(ピア・スタッフ)などがひとつのチームとなり、被告人が希望すれば裁判中に治療や支援を実際に体験できます。一区切りつくところまで治療をがんばれば、卒業という形で裁判手続きは完了。その後刑務所に行くことは免除され、社会に戻って治療や支援を継続できるシステムとなっています。
私がシドニーで見たドラッグ・コートを仕切っていたのは、長らく依存症治療に携わってきたベテラン看護師でした。法廷では、誰もがその看護師の豊富な経験と知識を尊重し、裁判官でさえ自分には依存症治療の専門性がないことを自覚しながら、裁判に取り組んでいた姿がとても印象的でした。
依存症に対して正しい知識や経験則を持っている裁判官はまだ少ないですが、いつか日本でもドラッグ・コートのように、裁判官が依存症に関する専門家や関係者(医師だけでなく、看護師や心理士、福祉職やピア・スタッフなど)を心から尊重し、依存症の人が裁判を通して自らの人生を『生き直す』ことができるような裁判システムを実現させたいです。そのためには、今ある裁判所の仕組みを、目の前にいる裁判官の意識を、少しずつ変えていく必要があります。それを実現するもう一歩先の工夫とは何なのかを日々模索し続けています。
このコラムの読者の皆さまも、この先、裁判手続きへの協力や支援を依頼されることがあるかもしれません。そして、それを依頼している弁護士はもしかしたら私かもしれません。そのときはできる範囲でご協力いただきたいと願っています。ぜひ笑顔でお会いしましょう!